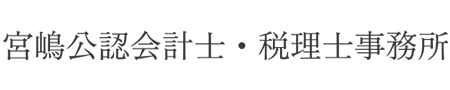日本の非営利セクターにおいて、財団法人は独自の重要な地位を占めています。奨学金の給付、美術館や博物館の運営、医学研究の助成、福祉施設の経営など、あるまとまった「財産」を原資として、公益目的のために事業を行う組織形態です。財団法人は、設立者から拠出された財産を適正に維持・運用し、その果実をもって社会貢献を行うという性質上、高度な財務的透明性とガバナンスが求められます。
その信頼性を担保する最も強力な手段の一つが、「公認会計士による監査」です。しかし、一般財団法人や公益財団法人の運営者であっても、どのような条件下で監査が法的に義務付けられるのか、あるいは任意で監査を受けるべきなのかについて、正確に理解されているケースは多くありません。特に、株式会社とは異なる「評議員会」などの機関設計や、独特な会計基準が存在するため、判断に迷うことも少なくないでしょう。
本記事では、財団法人の理事、評議員、事務局長の皆様に向けて、財団法人における公認会計士監査の法的要件、監査のメリット、適切な監査人の選び方から費用感に至るまで、実務に即して網羅的に解説します。
公認会計士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
財団法人で監査が必要になるケースとは?
財団法人とは?
財団法人の本質と「財産」の重要性
財団法人とは、「特定の目的のために拠出された財産の集まり」に対して法人格が与えられた組織です。「人の集まり」である社団法人とは対照的に、財団法人の中心にあるのはあくまで「財産」です。設立者(寄付者)が「このお金(または不動産など)を、こういう目的のために使ってください」と意思表示をして財産を拠出し、その財産を管理・運用するための組織として形成されます。
平成20年の公益法人制度改革により、従来の民法法人は「一般財団法人」と「公益財団法人」の二階建ての制度に再編されました。一般財団法人は、300万円以上の財産の拠出と定款の作成、登記のみで設立が可能であり、事業目的に公益性は必須とされません。一方、公益財団法人は、一般財団法人のうち、行政庁(内閣府または都道府県)から「公益認定」を受けた法人であり、税制優遇を受ける代わりに、厳格な公益目的事業の実施と財務規律が求められます。
非営利性と「分配の禁止」
財団法人も社団法人と同様に「非営利法人」です。これは利益を出してはいけないという意味ではなく、「利益(剰余金)を分配してはならない」という原則を指します。株式会社であれば株主への配当が可能ですが、財団法人にはそもそも「株主」や「社員(構成員)」が存在しません。設立者であっても、拠出した財産から利益の分配を受けることはできません。獲得した利益や運用益は、すべて法人の目的事業のために再投資されるか、将来の活動のために内部留保として蓄積されます。この「分配の禁止」と「財産の拘束性」が、財団法人の会計において非常に重要な意味を持ちます。
財団法人のガバナンス構造と評議員会
財団法人のガバナンス(統治)構造は、社団法人とは大きく異なります。社団法人には最高意思決定機関として「社員総会」がありますが、財団法人には社員がいません。その代わりに設置が義務付けられているのが「評議員」および「評議員会」です。
評議員会は、理事や監事の選任・解任、計算書類の承認、定款の変更など、法人の重要事項を決定する機関です。理事会は業務執行を行いますが、その監督機能を評議員会が担うという二層構造になっています。また、業務執行や会計をチェックする「監事」の設置も必須です。今回解説する「公認会計士による監査」は、これら内部機関によるチェックとは別に、外部の専門家が客観的に財務の適正性を証明する仕組みとなります。
公認会計士による監査とは何か?
外部監査の定義と社会的意義
公認会計士による監査とは、組織から独立した第三者の専門家が、法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書など)を検証し、その内容が会計基準に従って適正に表示されているかどうかについて意見を表明することです。
財団法人の場合、その原資は設立者からの寄付や、国・自治体からの補助金、運用益などで成り立っています。これらの資金が目的に沿って正しく使われているか、財産が毀損されていないかを証明することは、社会的な説明責任を果たす上で不可欠です。法人が自ら「正しくやっています」と主張するだけでは不十分であり、利害関係のない公認会計士が「間違いありません」と保証すること(監査報告書の発行)で初めて、対外的な信頼が確立されます。
監査業務の実務的プロセス
監査は決算期末に帳簿をパラパラと見て終わるものではありません。年間を通じた継続的なプロセスです。期中においては、法人の業務フローや承認プロセスなどの「内部統制」が有効に機能しているかをテストします。内部統制がしっかりしていれば、作成される数字の信頼性も高いと判断できるからです。
決算期末には、銀行残高確認書の入手、保有有価証券の時価評価の検証、固定資産の実査、未払金や未収金の網羅性確認など、詳細な実証手続を行います。財団法人の場合、基本財産や特定資産の取り崩しが適正な手続きを経て行われているかといった点も重要なチェック項目となります。
監事監査と会計監査人監査の違い
財団法人には必ず「監事」がいます。監事も会計監査を行いますが、監事の監査は「業務監査」を含む広範なものです。理事が善管注意義務を果たしているか、法令違反がないかといった職務執行全般を監視します。一方で、監事は必ずしも会計のプロフェッショナルであるとは限らず、また法人の内部機関としての性格も持ちます。
これに対し、会計監査人(公認会計士)による監査は、計算書類の適正性に特化した高度な専門的監査です。会計監査人は法人法上の「機関」として位置づけられ、監事や評議員会に対して独立した立場で会計に関する報告を行う義務を負います。大規模な財団法人では、監事と会計監査人が連携することで、より強固なガバナンス体制を構築することが求められます。
財団法人で公認会計士の監査が必要なケースとは?
財団法人において会計監査人の設置(公認会計士監査)が法律で義務付けられるケースは、その法人の規模や公益性の有無によって明確に線引きされています。ここでは、法定監査が必要となる要件と、法律上の義務はなくとも監査が必要となるケースについて詳述します。
一般財団法人で監査が義務付けられるケース
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)」において、会計監査人の設置が義務付けられるのは「大規模一般財団法人」に該当する場合です。
大規模一般財団法人とは、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が「200億円以上」である法人を指します。一般社団法人と同様の基準です。財団法人は多額の基本財産を保有しているケースが多いですが、純資産(正味財産)の額がいくら大きくても、負債が200億円未満であれば、法律上の監査義務はありません。
ただし、負債が200億円を超えるような一般財団法人は、外部からの借入金や預り金が巨額であることを意味し、その破綻が社会に与える影響が大きいため、公認会計士による厳格なチェックが求められるのです。
公益財団法人で監査が義務付けられるケース
公益財団法人の場合、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)」に基づき、より厳しい基準が適用されます。公益財団法人は、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とし、税制上の優遇措置も手厚いため、より高度な透明性が求められるからです。
具体的には、以下のいずれかの要件を満たす公益財団法人は、会計監査人を設置しなければなりません。
第一の要件は「収益の額」です。最終事業年度に係る損益計算書の収益の部の合計額が「1000億円以上」である場合です。 第二の要件は「費用および損失の額」です。最終事業年度に係る損益計算書の費用及び損失の部の合計額が「1000億円以上」である場合です。 第三の要件は「負債の額」です。最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が「50億円以上」である場合です。
一般財団法人の基準(200億円)と比較して、負債の基準が4分の1の「50億円」に設定されている点に注意が必要です。病院を経営する財団や、大規模な施設を建設・運営するために借入を行っている財団などは、この基準に抵触する可能性があります。また、行政庁が必要と認めた場合にも、監査の実施が求められることがあります。
法律上の義務はないが、定款で定めるケース(任意設置)
上記の法定要件(負債200億円や50億円など)に該当しない場合でも、財団法人が自らの意思で定款に「会計監査人を置く」旨を定め、登記することができます。これを「任意の法定監査」と呼びます。
一度定款に定めて登記すれば、会社法上の会計監査人設置会社と同様に、法的な監査を受ける義務が発生します。多くの財団法人がこの選択をする理由は、「社会的信用の獲得」です。特に、広く一般から寄付を募る場合や、公的な助成金事業を行う場合、監査済み財務諸表を開示することで、資金管理の透明性をアピールし、ステークホルダーからの信頼を得ることができます。
任意監査(合意に基づく監査)が必要なケース
会計監査人を法的に設置(登記)せず、契約に基づいて公認会計士の監査を受ける「任意監査」のケースも多々あります。
例えば、国や自治体からの補助金事業において、事業報告書に公認会計士の監査報告書を添付することが交付要綱で定められている場合です。また、金融機関から多額の融資を受ける際に、コベナント(財務制限条項)の一環として監査を受けることが条件となる場合もあります。 さらに、理事が交代するタイミングや、経理担当者の不正が疑われる場合などに、過去の会計処理の適正性を調査するためにスポットで監査を依頼するケースもあります。これらの任意監査は、目的に応じて監査の範囲を限定することも可能ですが、対外的な信用力を目的とする場合は、法定監査に準じたフルスコープの監査が行われることが一般的です。
会計監査人とは何か?
会計監査人の法的定義と位置づけ
会計監査人とは、法人法に基づいて財団法人に設置される機関の一つです。評議員会の決議によって選任され、法人の計算書類等を監査し、その結果を報告する権限と責任を持ちます。単なる外部委託先ではなく、理事会や評議員会、監事と並ぶ、法人のガバナンスを構成する法的な「機関」であることが重要です。そのため、会計監査人の氏名や名称は、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されます。
会計監査人の資格要件
会計監査人になれるのは、「公認会計士」または「監査法人」に限られます。税理士は、税務の専門家ですが、会計監査人として監査報告書にサインすることは法律上できません(公認会計士資格を併有している場合を除く)。
会計監査人の職務権限と責任
会計監査人の主な職務は、財団法人が作成した計算書類およびその附属明細書を監査し、会計監査報告を作成することです。この職務を遂行するために、会計監査人には強力な権限が与えられています。いつでも会計帳簿や資料を閲覧・謄写し、理事や職員に対して会計に関する報告を求めることができます。
一方で、その責任も重大です。任務を怠って財団法人に損害を与えた場合は、法人に対して損害賠償責任を負います。また、第三者(寄付者や債権者など)に対しても、悪意または重大な過失があった場合は損害賠償責任を負います。さらに、監査の過程で理事の職務執行に関わる不正行為や法令・定款違反を発見した場合は、直ちに監事に報告しなければなりません。必要に応じて、評議員会に出席して意見を述べることもあります。
会計監査人の選任について
選任の決議機関:評議員会
会計監査人を選任するのは、財団法人の最高監督機関である「評議員会」です。社団法人では社員総会がこれを行いますが、財団法人では評議員会が決議権を持ちます。理事会が会計監査人の候補者を選定し、評議員会に提案して承認を得るのが一般的な流れですが、法律上、会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定する権限は「監事」にあります(監事が複数の場合はその過半数)。
これは、監査される側である理事が、自分たちに都合の良い(甘い監査をする)監査人を選ぶことを防ぐための牽制機能です。実務上は理事が候補を探してきますが、最終的な決定権は監事と評議員会にあるという構造を理解しておく必要があります。
任期と再任の仕組み
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです。つまり、原則として1年ごとの契約となります。ただし、定時評議員会において別段の決議(解任や不再任の決議)がなされなかった場合には、自動的に再任されたものとみなされます。これにより、特段の問題がなければ、毎年煩雑な選任手続きを経ることなく、継続して監査を受けることができます。
公認会計士の監査費用相場
報酬決定のメカニズム
監査報酬(監査費用)は、定価があるわけではありません。「監査に要する時間(工数)」×「単価」の積上げで計算されます。 監査に要する時間は、法人の規模(資産総額や収益規模)、事業の複雑さ、拠点の数、そして何より「内部統制の整備状況」によって大きく変動します。経理処理が正確で、証憑書類が整理されており、内部チェック体制がしっかりしている法人は、監査人が確認すべき工数が減るため費用が安くなります。逆に、経理ミスが多く、資料の不備が散見される場合は、修正や追加確認に膨大な時間がかかるため、費用は高騰します。
規模別の相場目安
あくまで一般的な目安ですが、財団法人における監査費用の相場感は以下の通りです。
小規模な財団法人(資産総額数億円程度、事業内容がシンプル)であれば、年間200万円から400万円程度が目安となることが多いです。 中規模以上の法人や、複数の施設を運営している場合、あるいは公益財団法人で区分経理などの会計処理が複雑な場合は、500万円から1000万円、あるいはそれ以上になることもあります。 特に、全国に支部があるような大規模な財団法人の場合、支部の往査(実地調査)が必要となるため、旅費交通費も含めて費用はさらに大きくなります。
ショートレビュー(予備調査)の費用
初めて監査を受ける場合、いきなり本監査契約を結ぶのではなく、まずは「ショートレビュー(予備調査)」を行うことが一般的です。これは、監査人が法人の現状を把握し、監査を受けるための体制が整っているか(監査受入態勢)、どのような会計上のリスクがあるかを短期間で調査するものです。このショートレビューの費用は、数十万円から100万円程度が相場です。この調査結果に基づいて、本監査にかかる工数が見積もられ、最終的な監査報酬が決定されます。
財団法人が公認会計士を選ぶ際のポイント
公益法人会計基準への精通度
財団法人の会計は、株式会社の企業会計とは異なる「公益法人会計基準」に基づいています。特に公益財団法人や、移行認定を目指す一般財団法人の場合、この基準の適用は必須です。 この基準には、正味財産の増減計算や、収益事業と公益目的事業の区分経理など、独特の概念が含まれています。したがって、選定する公認会計士や監査法人が、この公益法人会計基準に精通しているかどうかは最重要ポイントです。企業会計の監査経験が豊富でも、非営利法人の監査経験が乏しいと、適切な指導や判断ができない可能性があります。
財団特有のガバナンスへの理解
財団法人には「評議員会」という独自の機関があり、理事会との権限分配や意思決定プロセスが社団法人や株式会社とは異なります。また、基本財産の維持義務や、不可欠特定財産の取り扱いなど、財産管理に関する法的規制も厳格です。監査人を選ぶ際は、単に数字を見るだけでなく、こうした財団法人特有のガバナンス構造や法的制約を深く理解しているかを確認する必要があります。
指導的機能の発揮(アドバイザリー能力)
多くの財団法人では、経理担当者が少人数であったり、公益法人会計に不慣れであったりすることがあります。そのため、監査人には、単に間違いを指摘して「不適正」とするだけでなく、どうすれば正しく処理できるかを指導・助言する姿勢が求められます。 もちろん、監査人は独立性を保つ必要があるため、決算書を代わりに作成することはできませんが、会計基準の解釈や内部統制の改善点について、丁寧に説明し、法人の自律的な成長を支援してくれる監査人を選ぶことが、長期的な法人運営にとって有益です。
監査チームの継続性と安定性
監査は、法人の歴史や背景、事業の特殊性を深く理解することで、より効率的かつ効果的に行えるようになります。そのため、担当する会計士が頻繁にコロコロ変わるような監査法人では、毎年同じ説明を繰り返さなければならず、法人の負担が増えます。監査法人を選ぶ際は、担当パートナーやマネージャーが長期的に関与してくれる体制があるか、法人の理念を理解しようとする姿勢があるかを確認しましょう。
財団法人が公認会計士を探す方法
日本公認会計士協会の検索システム
日本公認会計士協会のウェブサイトには、会員である公認会計士や監査法人を検索できる「会計監査人検索システム」などが用意されています。ここで「非営利法人」や「公益法人」を得意とする事務所を条件検索し、近隣の監査法人をリストアップすることができます。
業界団体や同業者からの紹介
同種の事業を行っている財団法人とのネットワークがある場合、既に監査を受けている法人から紹介してもらうのは非常に有効かつ安心な手段です。同業者の紹介であれば、その業界特有の事情(例えば美術館なら美術品の評価、研究助成なら助成金の管理など)に詳しく、実績も確かな監査法人である可能性が高いです。また、監査対応の雰囲気(厳格さや親切さ)についても事前に評判を聞くことができます。
顧問税理士や顧問弁護士からの紹介
普段から付き合いのある顧問税理士や顧問弁護士に相談するのも良い方法です。彼らは業務を通じて多くの公認会計士や監査法人と接点を持っており、法人の規模や風土に合った監査人を紹介してくれることが期待できます。特に、公益認定申請などで関与している行政書士や専門家がいれば、そのネットワークを活用するのも一手です。
インターネット検索と専門サイトの活用
「財団法人 監査」「公益法人 監査 公認会計士」などのキーワードで検索し、非営利法人の監査に注力している監査法人のウェブサイトをチェックします。公益認定等委員会の元委員が所属していたり、公益法人会計に関する書籍を出版していたりする事務所は、高い専門性を持っている証拠です。複数の事務所のウェブサイトを比較し、実績や理念を確認した上で面談を申し込みましょう。
財団法人が公認会計士を選ぶ際によくある質問の例と回答
Q1: 顧問税理士に監査もお願いできますか?
A1: 原則としてできません。監査において最も重要なのは「独立性」です。顧問税理士は、法人の側(作成者側)に立って決算書の作成を指導したり、記帳代行を行ったりする立場です。自分が関与して作成した決算書を自分で監査することは「自己監査」となり、客観性が保てないため、公認会計士法の倫理規定で禁止されています。したがって、監査は顧問税理士とは別の公認会計士や監査法人に依頼する必要があります。
Q2: 監査を受けるメリットは何ですか?(義務がない場合)
A2: 最大のメリットは「社会的信用の向上」です。外部の専門家による監査報告書があることで、寄付者、会員、行政庁、金融機関に対して、法人の財務状況が健全であり、資金が適正に使われていることを客観的に証明できます。これにより、寄付金が集まりやすくなったり、銀行融資がスムーズになったりします。また、内部的には、監査人からの指摘を通じて経理ミスや不正リスクを減らし、管理体制を強化できるというメリットもあります。
Q3: 監査契約までのスケジュールは?
A3: 余裕を持って準備することが重要です。決算期の直前に依頼しても、監査法人のリソース不足や予備調査の時間不足で断られるケースがあります。理想的には、監査を受けようとする事業年度が始まる前、遅くとも期中(決算日の半年前くらい)には選定を開始し、予備調査を経て契約を結ぶべきです。期末監査だけでなく、期中監査を実施することで、決算時の負担を分散させることができます。
Q4: 監査で「不適正意見」が出たらどうなりますか?
A4: 「不適正意見」(財務諸表が適正ではない)が出されることは、法人にとって極めて深刻な事態です。財務情報の信頼性が失われ、寄付の停止、役員の責任問題、金融機関からの融資引き上げ、最悪の場合は公益認定の取り消しや法人の存続危機に直結します。 通常は、いきなり不適正意見が出るのではなく、監査の過程で問題点が発見された段階で監査人から修正の勧告があり、法人がそれに従って修正すれば「適正意見」となります。不適正意見が出るのは、重大な粉飾や不正があり、かつ法人がそれを修正しない場合に限られます。
Q5: 監査費用を安く抑える方法はありますか?
A5: 監査費用は監査工数に比例します。したがって、監査人が効率的に監査を行える環境を整えることが費用削減の鍵です。具体的には、日々の経理処理を正確に行う、証憑書類を整理整頓しておく、内部統制を整備してミスを減らす、監査人からの質問に迅速に回答するなどです。法人の経理レベルが高く、監査リスクが低いと判断されれば、監査工数が減り、報酬の減額交渉が可能になる場合があります。また、複数の監査法人から相見積もりを取ることも有効です。
まとめ
財団法人において公認会計士の監査が必要となるケースは、法律で定められた「負債200億円以上の一般財団法人」や「負債50億円以上の公益財団法人」といった大規模法人だけではありません。定款による任意設置や、補助金・融資の要件、あるいはガバナンス強化を目的とした任意監査など、そのニーズは多岐にわたります。
特に財団法人は、設立者や社会から託された「財産」を管理・運用するという性質上、株式会社以上に高い透明性と説明責任が求められます。公認会計士による監査は、単なるコストや義務ではなく、法人の信頼性を守り、その公益的な活動を永続させるための重要なインフラ投資と言えます。
監査人を導入する際は、公益法人会計基準への専門性はもちろん、財団法人特有の評議員会制度などのガバナンス構造への理解、そして何より法人の理念を尊重し、共に歩んでくれる指導的な姿勢を持ったパートナーを選ぶことが成功の鍵です。本記事が、皆様の法人にとって最適な監査体制の構築と、より良い法人運営の一助となれば幸いです。
公認会計士をお探しの方は、宮嶋公認会計士・税理士事務所へお問合せください(初回無料相談)
この記事の作成者
宮嶋 直 公認会計士/税理士
京都大学理学部卒業後、大手会計事務所であるあずさ監査法人(KPMGジャパン)に入所。その後、外資系経営コンサルティング会社であるアクセンチュア、大手デジタルマーケティング会社であるオプトの経営企画管掌執行役員兼CFOを経験し、現在に至る。